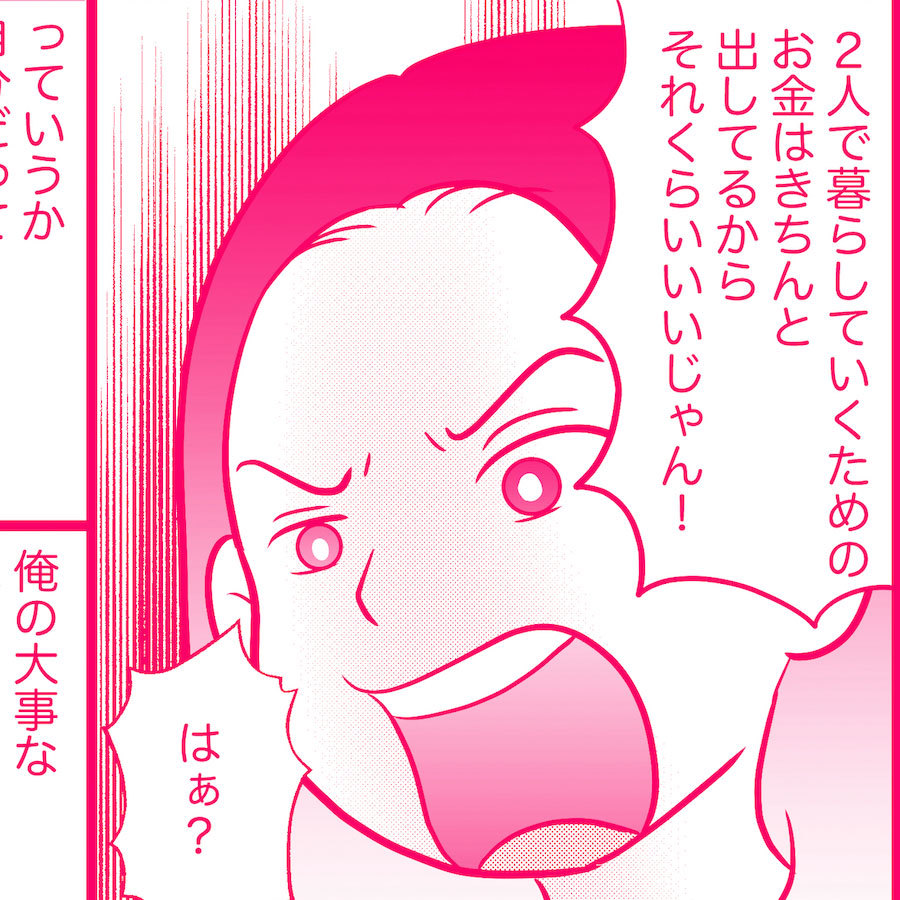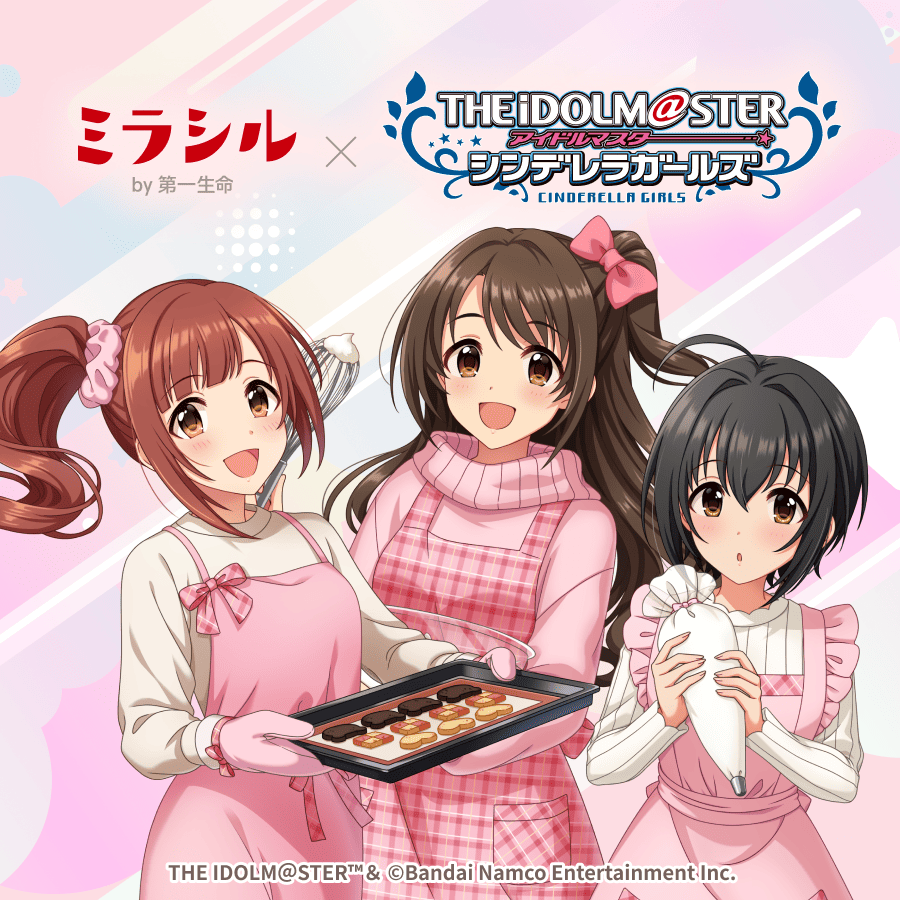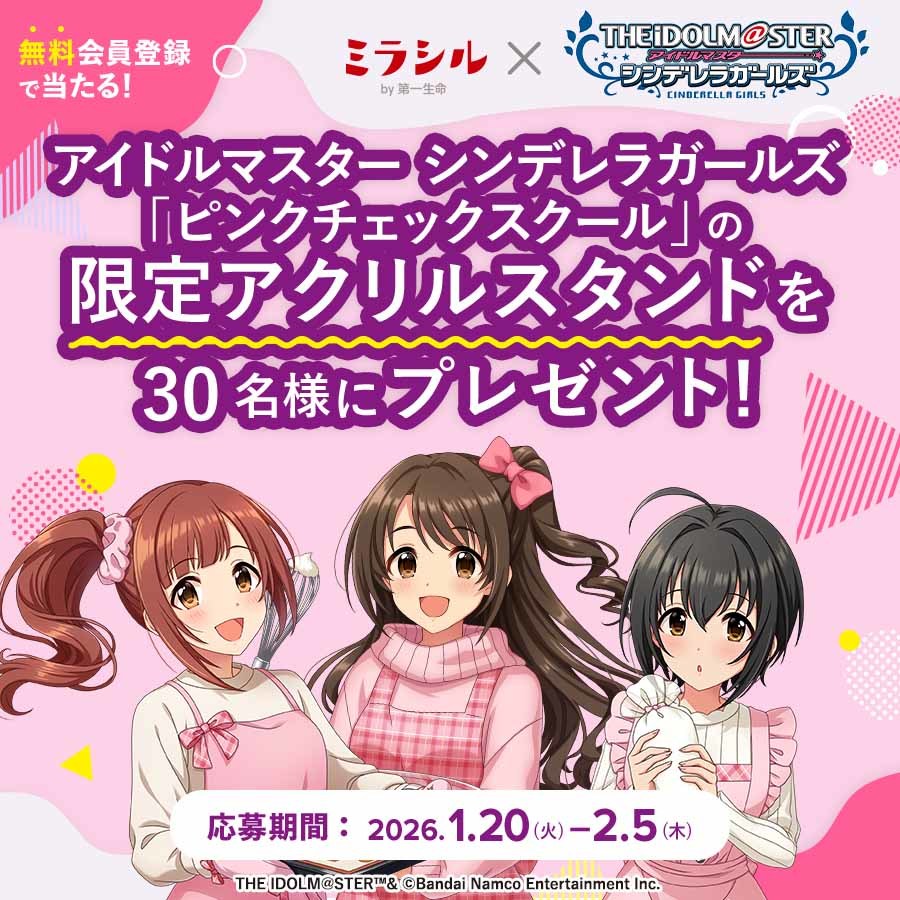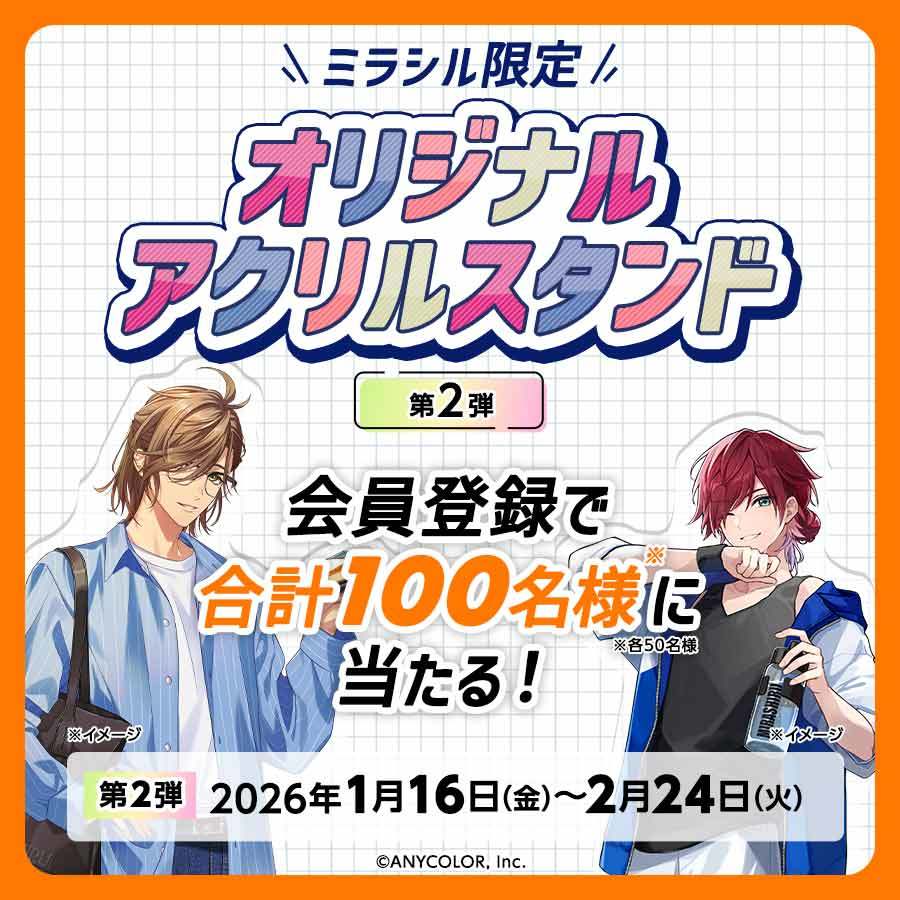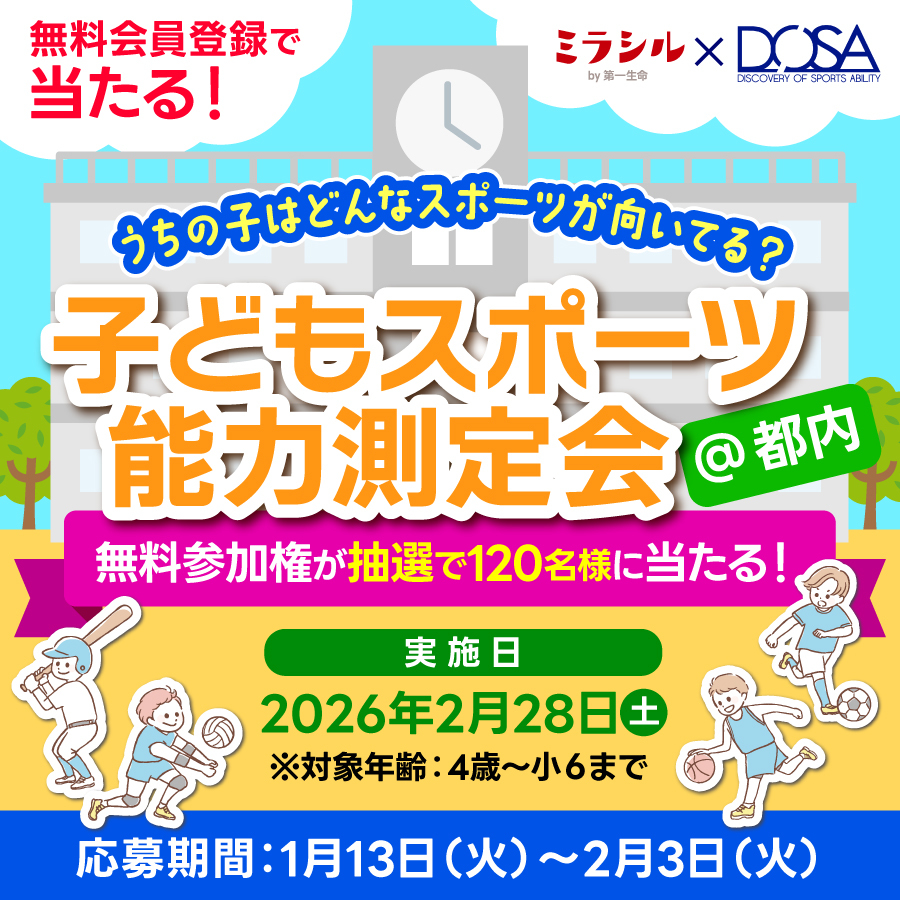食べ過ぎて気持ち悪い!対処法や防止のポイントを医師に聞いてみた。
「歓送迎会で飲み会続きだった」「ストレス発散のためにドカ食いしてしまった」。ついうっかり食べ過ぎてしまうつらいシチュエーションは、誰にでも経験があるのではないでしょうか。翌日まで残る胃もたれは、できれば二度と味わいたくないものです。
この記事では、胃腸の不調に詳しい消化器内科医の吉良文孝先生に、食べ過ぎのときに役立つ楽な姿勢や薬の飲み方、NG行動など、知っておきたい「食べ過ぎたときの対処の仕方」を伺いました。
目次
食べ過ぎたとき、体はどんな状態?

食べ過ぎというと、胃全体にパンパンに食べ物が詰まっている状態をイメージする人もいると思いますが、実は多くの場合、「胃の入り口に近い場所に食べ物がとどまっている状態」をいいます。
普通なら、食べたものはゆっくり胃の入り口から奥のほうへと運ばれていき、消化されるので苦しくありません。
しかし、急に食べ物が口から大量に流し込まれたり、ストレスなど何らかの理由で胃の働きが悪くなっていたりすると、胃の食べ物を奥に運ぶ機能が弱まってしまいます。
そのため胃の入り口に食べ物がとどまってしまい、食べ過ぎて苦しいと感じてしまうのです。
食べ過ぎて気持ち悪い!何をすべき?

食べ過ぎて気持ち悪いときは、それ以上食べるのをやめて、じっとして安静にすることが大切です。そのほか、苦しいときにやっておきたい対処法について解説します。
ゆったりした服に着替え、横になる。
ベルトをしているなら、おなかを締めつけないように緩めましょう。着替えられる環境にあるときは、部屋着などのゆったりした服装に着替えます。
横になるときは、自分が「楽だな」と思う体勢をとります。人それぞれ胃の状態は違うので、体の右側を下にすると楽な人、うつぶせのほうがいい人など個人差があります。ただ一般的には、少し背中を丸めておなかを抱え込むようなポーズだと、おなかにかかる圧力が減るため、楽になる人が多いようです。
また、胃の構造上、体の左側を下にして寝ると、胃酸の食道への逆流を防げます。そのため、吐き気がある人は、左側を下にして横になると症状がおさまりやすくなります。
胃薬はおなかに余裕ができてから飲む。
「気持ち悪い」「吐きそう」といった差し迫った症状があるときは、胃薬と一緒に飲む水が胃に入るだけで苦しくなることもあるので、胃薬を飲むのは時間がたって少し胃が楽になってきたタイミングにしましょう。
なお、胃薬には、口の中で溶けて水なしで飲めるタイプもあります。そのような薬であれば、早めに飲んでも苦しくなることは少ないです。
また、メントールなど清涼感のある成分が入っている胃薬は、胃の手前にある食道に届くだけでも一時的にはスカッとする効果があるので、あまりに症状がつらいときは症状のピーク時に飲んでもいいでしょう。
無理に吐かない。
吐き気があっても、無理やり吐こうとするのは体に負担がかかるのでおすすめしません。とはいえ、吐きたいのに我慢するのもつらいので、「吐いたら吐いたでしょうがない」という心構えでやりすごしましょう。胸のむかつき程度なら、コップ1杯の水を飲むとスッキリすることがあります。
早く寝る。
眠れない・眠くない場合は別ですが、あとはもう寝るだけという状態なら、そのまま寝てしまうことをおすすめします。「食後におなかいっぱいの状態で寝ると体によくない」といわれることもありますが、食べ過ぎで苦しい状態ならむしろ寝てしまったほうが、楽になる場合もあります。
食べ過ぎたときの対処法は?

食べ過ぎてつらい状況をなるべく長引かせたくない、早く元の調子に戻りたいというときに役立つ対処法を知っておきましょう。
翌日は無理に食事を摂らなくてもいい。
食べ過ぎで胃もたれしているときや、翌日に不調を持ち越して胃がムカムカしているときは、無理に固形物を摂る必要はありません。白湯などを飲んで水分を摂っていれば、だんだん胃が働き出して食事も摂りやすくなります。
食べられるようになったら、本調子になるまで、「まだまだ食べられそうだ」と感じる腹四分目くらいの量にとどめておきましょう。ただし、揚げ物や、辛すぎる料理は、少量でも胃の動きが止まりやすいのでおすすめしません。
炭酸飲料・冷たい飲み物・アルコールは避ける。
水分は飲みたいものを飲んで構いませんが、おなかを刺激する炭酸飲料や、よく冷えた飲み物は胃に負担がかかるので避けたほうがいいでしょう。また、アルコールは胃の「ぜん動運動」と呼ばれる筋肉の動きを抑制して、不調を長引かせる原因になるので避けましょう。
腹ごなしの運動は控える。
よく「腹ごなしに運動する」といいますが、食べ過ぎてはちきれそうなほど苦しいときには、胃がまったく動かない状態になっています。体を動かすとかえって気持ち悪くなり、逆効果に終わることもあるので控えたほうがいいでしょう。
食べ過ぎを防ぐためのポイント。

「つい食べ過ぎてしまうのを防ぎたい」という人にぜひ気をつけてほしいポイントをまとめました。
スピード・温度・脂質の量に注意。
まず注意してほしいのは、「スピード・温度・脂質の量」の3つです。
胃に急激に食べ物が流し込まれると、胃の動きが止まってしまいます。よくかんでゆっくり食べたほうが胃に負担がかかりませんし、食べているうちに満腹中枢が刺激されて満腹感を得やすくなるので、食べ過ぎを防げます。唾液や消化液が分泌されて消化しやすくなるというメリットもあります。
また、極端に冷たいもの、脂質が多いものも同様に胃の動きを悪くするのでおすすめしません。一番よくないのは、「濃厚で脂ギトギトなできたてラーメン」などの一気食い。胃に過度な負担がかかり動きを止めてしまうので避けましょう。
メリハリをつけて、「ながら食べ」をしない。
1人で食事をするとき、スマートフォンやテレビなどを見ながらダラダラ食べていると、気がそれているので腹具合がわからず、ついつい食べ過ぎてしまうことがあります。「ながら食べ」をやめて、食事以外のことに気を向けすぎないようにしましょう。
毎食ボンヤリ食べるのではなく、「今日は1人だから少なめにしよう」「友達との食事だからしっかりめに食べよう」など、意識して毎食のメリハリをつけることをおすすめします。
不快感が続くようなら病院へ。
しょっちゅう食べ過ぎによる気持ち悪さを感じる人は、消化器内科などの医療機関の受診をおすすめします。自分では食べ過ぎだと思っていたけれど、病気だったり、ストレスで自律神経のバランスが崩れていたりと、別の理由で胃の働きが低下している人も実は多いです。
「腹八分目以下」を心がけよう。

「急いでドカ食いしない」「ほどほどの温度」「脂質が多いものを避ける」の3つを心がけるだけでも、食べ過ぎに関連する不調をかなり防げるはずです。また、満腹まで食べるのは胃にはよくありませんので、できるだけ「腹八分目以下」を心がけてみてください。
そして、飲み会など食べ過ぎが心配なイベントの前には、胃薬を飲むなどの対処をしておくと、より安心です。
写真/PIXTA、Getty Images
【監修者】吉良 文孝
東長崎駅前内科クリニック院長。日本消化器病学会認定消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医などの資格を保有。東京慈恵会医科大学卒業後、東京警察病院にて初期臨床研修。JCHO東京新宿メディカルセンター(旧東京厚生年金病院)や都内内科クリニック・健診専門クリニック・医師会などでの勤務を経て、2018年より現職。
※ この記事は、ミラシル編集部が取材をもとに、制作したものです。
※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。
※ 記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。