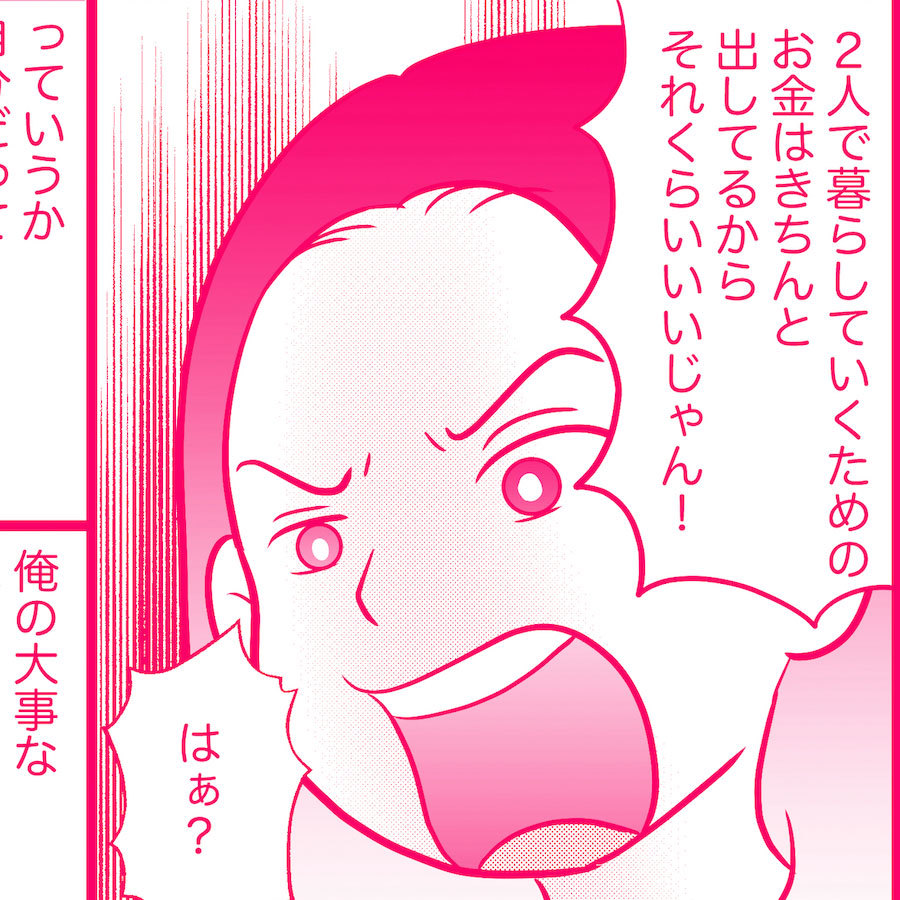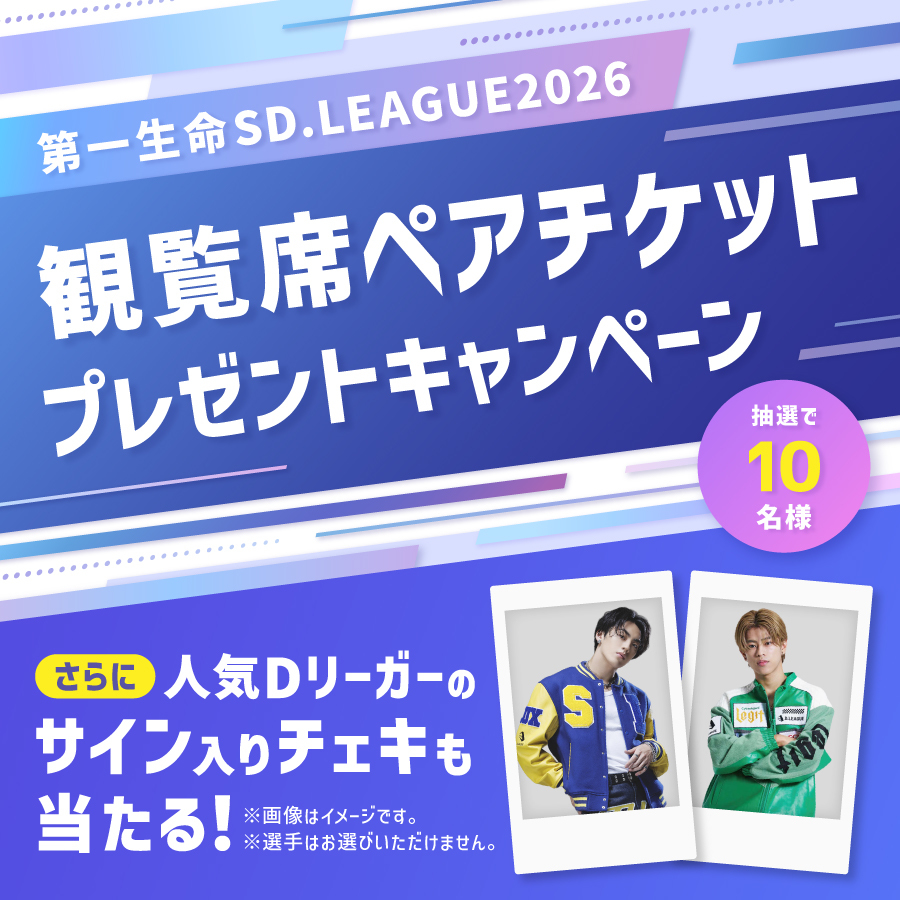カフェイン過敏症とは?症状やカフェイン中毒との違いをチェック
コーヒーや緑茶など、日常生活のなかで身近な飲み物に含まれているカフェイン。近年ではエナジードリンクやカフェイン含有の錠剤もよく飲まれるようになり、とりすぎによる健康被害も問題になっています。
そこで、そもそもカフェインとはどんなものなのか、摂取しすぎると体にどんな影響があるのか、救急の現場で多くの急性カフェイン中毒患者を診療している医師の上條吉人先生に伺いました。
目次
- そもそもカフェインってどんなもの?
- カフェインが体に与える影響は?
- カフェインで体調が悪くなった?
- カフェインによる体調不良への対処法。
- カフェインとの相性をチェックしよう。
- カフェインを多く含む飲食物は?
- カフェインとの上手なつき合い方。
- 【まとめ】摂取しすぎには注意!自分の適量を知ること。
そもそもカフェインってどんなもの?

カフェインはコーヒー豆以外にも、お茶の葉やカカオ豆(チョコレートやココア)、以前はコーラの原料に使われていたコーラナッツ、ガラナなどに含まれている食品成分の1つです。昔から嗜好品として摂取されてきました。
カフェインが体に与える影響は?
疲れたり眠くなったりしたときに、お茶やコーヒーを飲んで一息つくと、気分がシャキッとしますよね。これは、カフェインに中枢神経を刺激して覚醒させる作用があるため、眠気を抑えたり、だるさや疲労感を軽減させたりする効果があるからです。
夜、寝る前にコーヒーやお茶を飲むと寝つけなくなるのもこのためで、ほかにもコーヒーを飲むとトイレが近くなるというように、利尿作用もあります。
風邪薬や鼻炎薬などにカフェインが含まれているのは、薬に含まれる抗ヒスタミン剤による眠気を抑え、風邪によるだるさや疲労感を軽減するためです。この効能を利用して、眠気や倦怠感を抑え、集中力を高めるための錠剤も販売されています。
過剰にとるとこんな影響も。
カフェインは適切に摂取すれば、だるさや眠気を軽減させるなどのよい効果が期待できると知られています。しかし、過剰に摂取すると、次のような悪い影響もおよぼします。
参考:農林水産省「カフェインの過剰摂取について」(2024)
カフェインの過剰摂取による身体的影響。
中枢神経が刺激されるため、不眠・めまい・震えが起こります。また、心臓が刺激されて心拍数の増加や動悸も起こります。消化管が刺激されて、吐き気・嘔吐・下痢が起こることもあります。
人によっては高血圧のリスクが高くなる可能性や、妊婦が高濃度のカフェインを摂取した場合には、胎児の発育を妨げる可能性も報告されています。
参考:農林水産省「カフェインの過剰摂取について」(2024)
カフェインの過剰摂取による精神的影響。
中枢神経を過剰に興奮させて、不安・イライラ・不穏や興奮などを引き起こします。じっと落ち着いていられなくなるため、ADHD(注意欠如・多動症)と誤診されるケースもあります。
また、パニック障害のある人は、カフェインによって呼吸数や心拍数が上がり、めまいや不安が起きることで、パニック発作を誘発してしまいます。
生まれつき何事にも繊細な気質のHSP(ハイリー・センシティブ・パーソン)の人は、カフェインにも過敏に反応するケースが多いようです。
カフェインで体調が悪くなった?

カフェインをたくさん摂取することで、吐き気やイライラなど、さまざまな症状が出ることがあります。コーヒーやお茶・エナジードリンクなどを飲んで具合が悪くなったら、カフェイン過敏症やカフェイン中毒かもしれません。
カフェイン過敏症
カフェイン過敏症とは、摂取量に関係なく、カフェインに対して過剰に反応し、カフェインの作用が出ることです。アルコールに対する耐性が弱い人がビールを一口飲んだだけでも気分が悪くなってしまうのと同じで、カフェインに対する耐性が弱い人は、カフェインを少量とっただけで、呼吸数や心拍数の増加など、カフェイン中毒の症状が現れます。
最近よく聞かれるカフェイン過敏症ですが、実は「カフェイン過敏症」という病名は存在しません。このため、特別な検査や治療方法・治療薬などはなく、カフェインをいかにとらないかが予防・対処法になります。
カフェイン中毒
カフェイン中毒とは、カフェインを多量に摂取することで発症する中毒症状のことです。
症状としては、頻回の(間を置かず何度も)嘔吐・不安・イライラ・不穏・興奮・錯乱・けいれん発作・呼吸数や心拍数の増加・胸痛など。血液の異常としては、低カリウム血症や低リン血症・高血糖・高乳酸血症・横紋筋融解症などを起こすこともあります。最悪の場合には、心室頻拍や心室細動といった致死的な不整脈で心停止に至ることもあります。
こんな症状を聞くと「カフェインは危ない!」と怖くなるかもしれませんが、基本的に、飲み物で命に関わるほどの多量のカフェインを、短時間で摂取することはできないので安心してください。
なぜなら、カフェインの致死量は一般的には5gから10g(※)とされていて、これは、たとえば1杯に60㎎のカフェインが含まれているコーヒーであれば、一度に80杯以上も飲まなくてはならないからです。
※ 個人差があります。
近年、カフェインの急性中毒で救急搬送される患者さんが増えていますが、その多くは、簡単に大量のカフェインをとることができる錠剤の過剰摂取によるものです。
急性カフェイン中毒は放っておくと致死率が高くなりますが、すぐに適切に治療すればほぼ再発もなく完治するケースがほとんどです。重症になった場合の治療には、血液透析法が非常に有効です。
カフェイン依存症
依存症は、あるものを繰り返して摂取しているうちに出る症状で、摂取していないとそれが欲しくてたまらない「精神依存」と、その物質が切れたときに禁断症状(または離脱症状)が現れる「身体依存」があります。
カフェインは依存性がある物質のため、続けてたくさんとっていると、依存症になってしまいます。カフェインをとらないとソワソワして落ち着かない・イライラする・不安になる・とりたくてたまらないという人は、カフェイン依存症になっているかもしれません。
カフェイン依存症を改善するには、コーヒーやお茶など、カフェインを含む飲料の摂取量を減らすこと。またはカフェインレスの飲み物に変えるなどして、摂取量を減らしましょう。また、コーヒーが飲みたくなったら代わりにガムを噛むなどして、気分を変えることも有効です。
カフェインによる体調不良への対処法。

カフェインによる体調不良を感じた場合、いくつかの対処法があります。
水分を摂取して血中カフェイン濃度を下げる。
こまめに水分をとることで体内のカフェイン濃度を薄め、尿からカフェインや活性代謝物の排出を促すことができ、次第に回復します。なお、緑茶や紅茶などにはカフェインが含まれているため、水分補給はカフェインを含まないミネラルウォーターやスポーツドリンクでするとよいでしょう。
軽く運動する。
症状が軽い場合であれば、ウォーキングなどの軽い運動をすることで、カフェインを早めに体外に排出する効果が期待できます。
病院で胃の中に活性炭を投与する。
呼吸困難・動悸・頭痛・下痢・嘔吐・けいれんなどの症状がある場合は早めに病院に行きましょう。病院では胃の中に活性炭を投与して消化管内のカフェインを吸着させて便と一緒に排泄させたり、点滴したり、重症の場合は血液透析法を行うなどの治療を行います。
カフェインとの相性をチェックしよう。
カフェインとの相性を「カフェイン感受性」と言います。カフェイン感受性は、体格によっても違いますし、年齢・病歴・医薬品の使用・心身の健康状態などによっても違います。
さらに、カフェインを分解する肝臓の酵素「CYP1A2」の働きは、個人差が大きいこともわかっています。唾液採取による遺伝子検査を受けることで、この働きの度合いを調べることができます。
日常的にカフェインを摂取している人は、一度確認してみることもおすすめです。
カフェインを多く含む飲食物は?
カフェインを多く含む主な食品は以下のとおりです。日常的に嗜好品として飲まれているものはコーヒーや緑茶や紅茶などのお茶類ですが、最近よく飲まれるようになったエナジードリンクにも多く含まれています。
勉強するときの眠気覚ましや、頭がシャキッとするなどの理由で愛飲する方も多いようですが、エナジードリンクにはコーヒーやお茶より多くのカフェインが含まれているものもあります。飲みすぎによる健康への悪影響も知られているので十分に注意してください。
●食品中のカフェイン濃度(カフェイン含有量が多い順に掲載)
| 食品名 | カフェイン濃度 | 備考 |
| エナジードリンク又は眠気覚まし用飲料 (清涼飲料水) | 32~300mg/100mL (製品1本当たりでは、36~150 mg) | 製品によって、カフェイン濃度及び内容量が異なる。 |
| 玉露(浸出液) | 0.16g/100mL (=160mg/100mL) | 浸出法:茶葉10g、60℃湯60 mL、2.5分 |
| インスタントコーヒー(粉末) | 4.0g/100g (2g使用した場合、1杯当たり80mg) | ― |
| 抹茶(粉末) | 3.2g/100g (お湯70mLに粉末1.5 gを溶解した場合、カフェイン含有量48mg) | ― |
| コーヒー(浸出液) | 0.06g/100mL (=60 mg/100mL) | 浸出法:コーヒー粉末10g、熱湯150mL |
| 紅茶(浸出液) | 0.03g/100mL (=30mg/100mL) | 浸出法:茶葉5g、熱湯360 mL、1.5~4分 |
| ウーロン茶(浸出液) | 0.02g/100mL (=20mg/100mL) | 浸出法:茶葉15g、90℃湯650 mL、0.5分 |
| せん茶(浸出液) | 0.02g/100mL (=20mg/100mL) | 浸出法:茶葉10g、90℃湯430 mL、1分 |
| ほうじ茶(浸出液) | 0.02g/100mL (=20mg/100mL) | 浸出法:茶葉15g、90℃湯650 mL、0.5分 |
| 玄米茶(浸出液) | 0.01g/100mL (=10mg/100mL) | 浸出法:茶葉15g、90℃湯650 mL、0.5分 |
(注)エナジードリンク又は眠気覚まし用飲料(清涼飲料水)は、市販11製品の成分表示等(2015年12月22日、農林水産省調べ)
コーヒー、インスタントコーヒー、茶類は、「日本食品標準成分表2020(八訂)」
出典:農林水産省「カフェインの過剰摂取について」(2024)をミラシル編集部にて一部加工
気を付けて!知らないうちにカフェイン中毒になりやすいケース。
カフェインの過剰摂取が原因で病院に運ばれてくる人の多くは、カフェインの錠剤を大量に摂取して運ばれてきます。錠剤だと飲料よりもはるかに手軽にカフェインを大量に摂取できてしまうので、自分ではそんなに大量摂取していないと考えていても、カフェイン中毒になってしまう可能性があります。
また、エナジードリンクとアルコールを混ぜて飲む「エナジードリンク割」は非常に危険です。
エナジードリンクは、「酔ってぼんやりしてきたな」「眠いな」といったアルコールによる機能低下の感覚を覆い隠して覚醒させるため、結果的にアルコールを飲みすぎてしまい、カフェインとアルコールを大量に摂取する危険性があったり、カフェインとアルコールによる利尿作用により脱水症状を引き起こしたりします。
カフェインとの上手なつき合い方。

とり方しだいで毒にも薬にもなるカフェイン。毎日の生活のなかで効果的に取り入れるには、どのようにつき合っていけばよいのでしょう。
短時間でたくさんとりすぎない。
カフェインは、適切な量であればリラックスできたり、眠気やだるさを抑えたりと、有効性の高い成分です。仕事や家事の合間にコーヒーやお茶を飲んで気分をリフレッシュする人も多いでしょう。
重要なのは、短時間に大量に摂取しないこと。カフェインをとって気分が悪くなる・イライラする・ドキドキするなどの症状を感じたら、その日はカフェインをとるのを控えてください。また、カフェインを含む医薬品を服用する場合には、コーヒーやエナジードリンクなどは控えましょう。
そして、飲むと眠れなくなる・トイレが近くなるなど、カフェインによってどのような影響が出やすいのかを知っておくことも大事です。なお、個人差が非常に大きいのですが、カフェインの効果が薄れるまでの時間は平均4時間程度とされています。飲む時間や量など、自分の体にあわせた飲み方を工夫してください。
1日の適切な摂取量は?
カフェインで特に注意したいのが摂取量ですが、カフェインを一生涯摂取し続けたとしても、健康に悪影響が生じないと推定される1日当たりの摂取許容量(ADI:Acceptable Daily Intake)については個人差が大きいことから、日本でも海外でも設定されていません。しかし、国際機関などからは次のようなアドバイス・注意喚起等がなされています。
米国食品医薬品局(FDA)
健康な大人ならば、1日当たり400mg(コーヒーでは4~5カップ程度)までであれば、カフェインによる健康への危険な悪影響はないとしています。
欧州食品安全機関(EFSA)
大人では、体重1kg当たりカフェイン摂取量が約3 mgであれば急性毒性の懸念はないとしています。たとえば、体重70kgの大人であれば、1回当たり200mgのカフェイン摂取であれば健康リスクは増加しないとしています。
カナダ保健省
18歳以上の大人は1日当たり400mgまで、妊婦や母乳で保育している母親は1日当たり300mgまでとしています。18歳までの子どもや青少年は1日当たりの体重1kg当たりカフェイン摂取量を2.5mgまでとしています。
参考:農林水産省「カフェインの過剰摂取について」(2024)
【まとめ】摂取しすぎには注意!自分の適量を知ること。
多くの効能があるカフェインですが、とりすぎれば依存症や中毒になるなど体に悪影響をおよぼします。摂取量の目安はあるものの、耐性や体質は人それぞれ。自分の適量を知り、カフェインとおいしく上手につき合っていきましょう。
写真/PIXTA
【監修者】上條 吉人
埼玉医科大学病院臨床中毒センター長。埼玉医科大学医学部臨床中毒科教授であり、臨床中毒科診療部長を務める。専門は救急医学、精神医学、中毒学。救急医療の現場で多くの急性中毒患者の治療にあたる。
※ この記事は、ミラシル編集部が監修者への取材をもとに、制作したものです。
※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。
※ 記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。