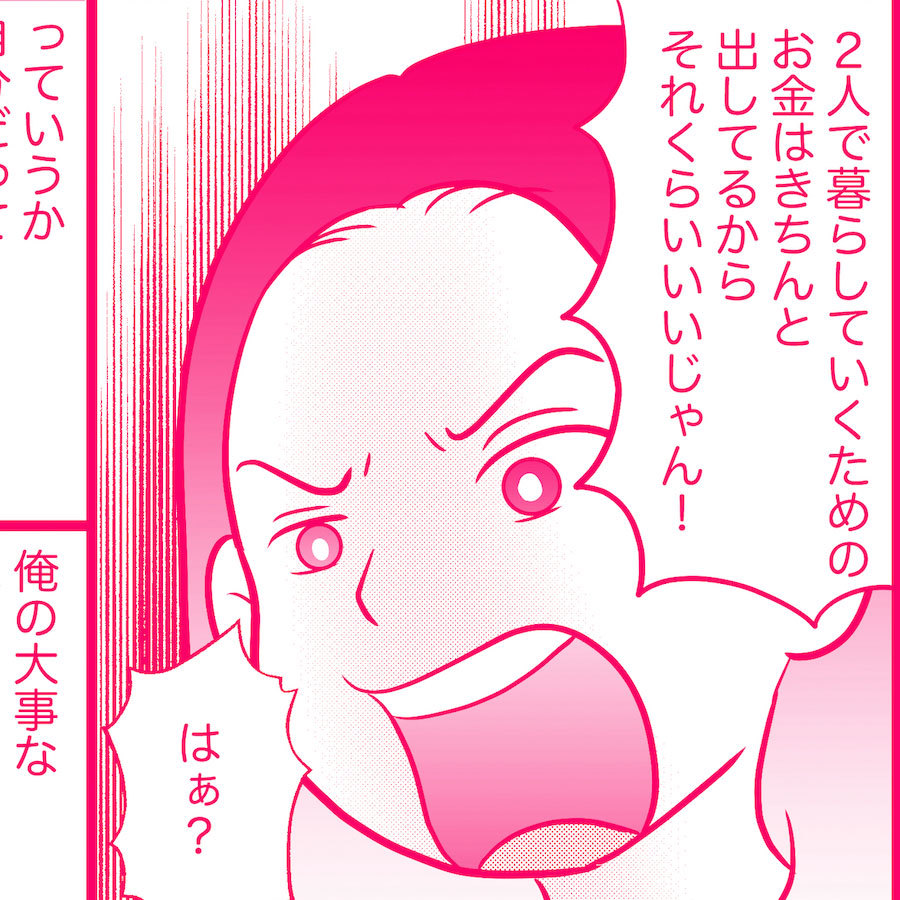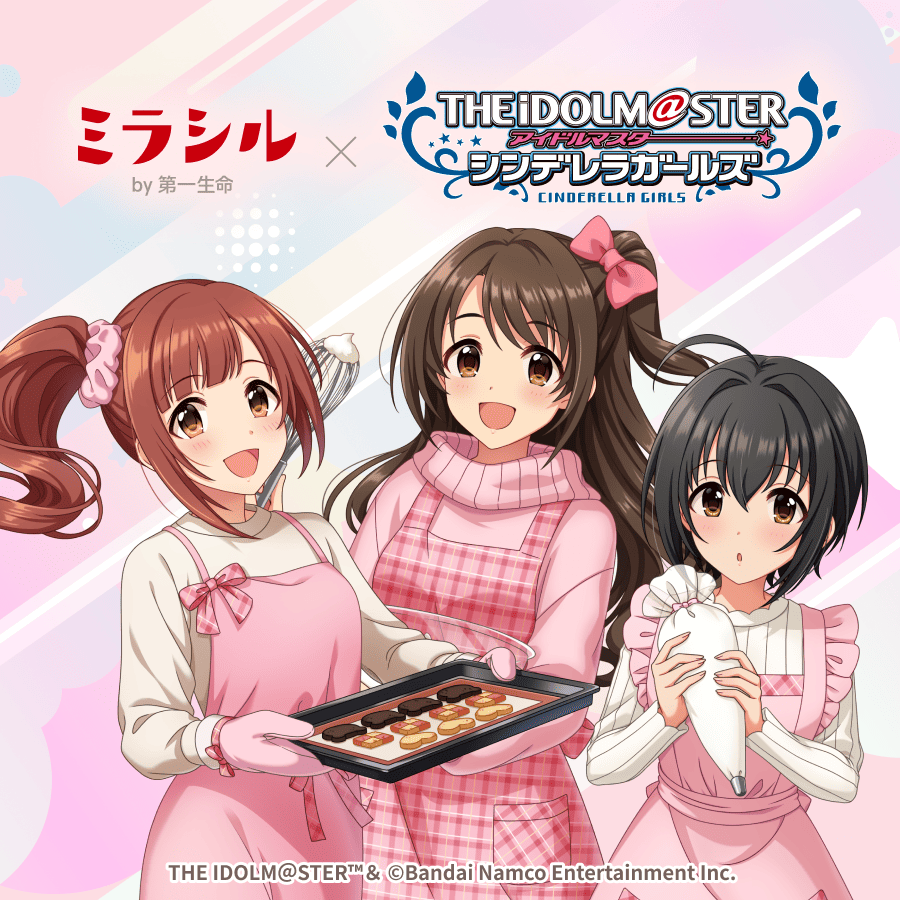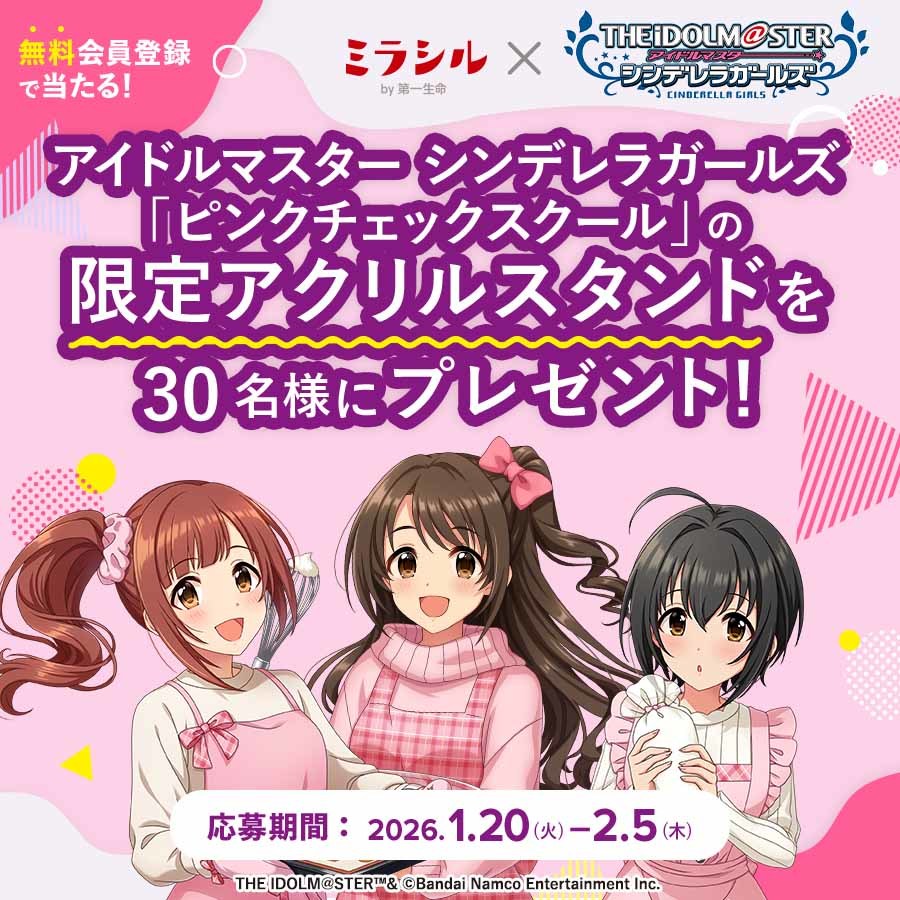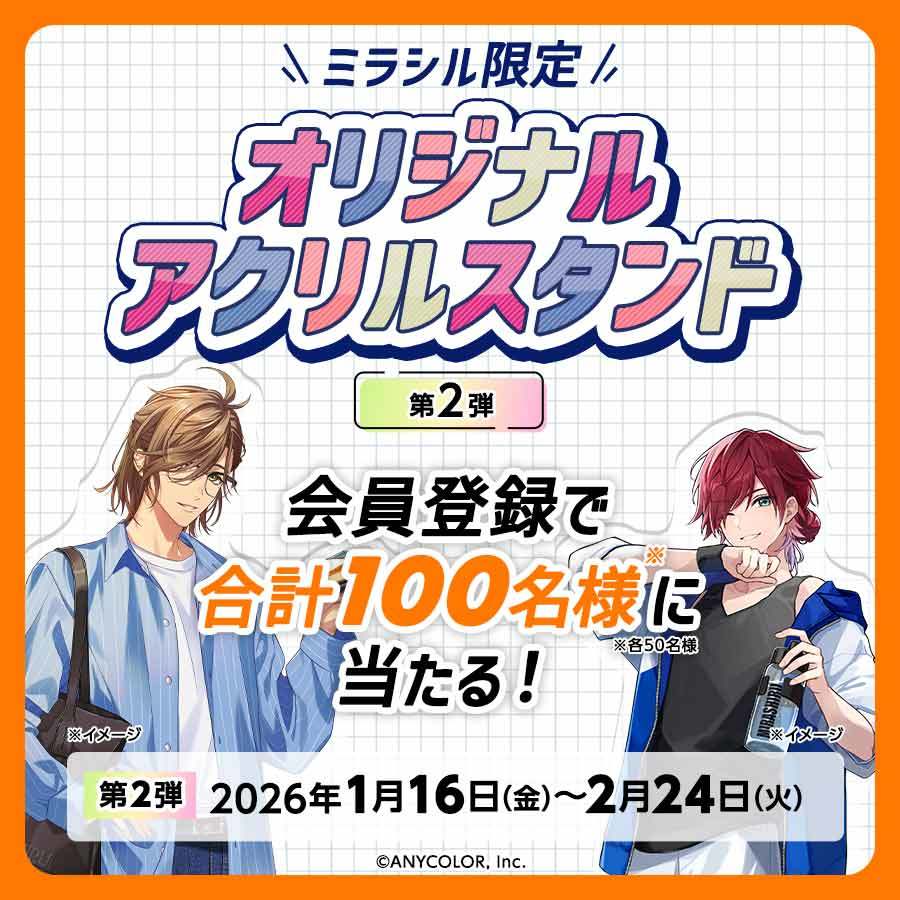【医師解説】休肝日の効果って?どうやって実践・継続したらいい?
毎日の晩酌が習慣化していたり、飲み会が続いていたりして、なんとなく不調を感じるようになってはいませんか? 「うまくお酒と付き合うためには『休肝日』を設けるといい」とよく聞きますが、実際の効果やメリットはなんとなくあいまいなまま、その日の気分で「飲むか、飲まないか」を決めている人もいることでしょう。
今回は、肝臓が専門の内科医で、自身もお酒がお好きな浅部伸一さんに、休肝日の効果や、飲みすぎを防ぐおすすめの実践法まで、医学的なエビデンスをもとに解説していただきました。
目次
休肝日にそもそも意味はあるの?

「休肝日」という造語は、私のようなお酒好きはもちろん、一般的にもよく知られた言葉です。しかし実は、1日お酒を抜くとどんな効果があるのか、何日間お酒を抜けば肝機能が回復するかなど、明確なことは明らかになってはいません。
お酒の「適量」は、体重・性別・年齢・アルコール分解能力の違いなどによって異なり、個人差が大きいもの。したがって、医学的な立場から適量を定めるのは難しいのですが、少なくとも休肝日を設けることで肝臓も体も休まるのは間違いなく、意味のある行為といえます。
実は、休肝日より「アルコールの総摂取量」が重要。
「休肝日」の字面から、多くの人は「週に〇日、肝臓を休める日をつくるのがいい」と考えがちですが、実は休肝日のペースよりも「アルコールの総摂取量」が重要なのです。
仮にいくら週2日、休肝日を設けていたとしても、そのほかの日に浴びるようにお酒を飲んでいては体への負担は大きいまま。さらに、翌日に残るほどお酒を飲んだにもかかわらず、連日飲酒をすることはかなりの負担になります。逆に、毎日お酒を飲んでいても、その量が少量であれば、健康に何ら問題ないというケースもあります。
したがって休肝日のメリットを医学的に考えるなら、「休肝日によりアルコールの総摂取量が減ることで、体への負担が軽くなる」ということになります。
種類別のアルコール含有量と、適切な量は?
では、いったいどれくらいの量のお酒を飲むのが適切なのか。
個人差はありますが、たとえば厚生労働省では、生活習慣病のリスクを高める飲酒量として、1日あたりの平均純アルコール摂取量を、男性では40g以上、女性では20g以上と定めています。これをもとにするなら、お酒で健康を害するリスクをある程度低減するには、純アルコールの摂取量を1日20g以下に抑える必要があるということです。
ちなみに一般的なお酒の種類と度数、純アルコール20gに相当する量は以下の通りです。
| 種類 | 度数 | 純アルコール20gを含む量 |
| ビール | 5% | 500ml |
| 日本酒 | 14%~15% | 約180ml |
| 焼酎 | 25% | 100ml |
| ワイン | 14% | 約180ml |
| ウイスキー | 43% | 60ml |
| 缶チューハイ | 5%/7% | 約500ml/約350ml |
参考:厚生労働省「習慣を変える、未来に備える あなたが決める、お酒のたしなみ方」(2024年)
お酒が好きな人にとっては、純アルコールの摂取量を20g以内に抑えるのは簡単ではないかもしれませんが、これらはあくまで目安です。1日20gを守らなければ間違いなく体に問題が起きるというわけではありません。ただ一方で、お酒を少しでも飲む時点で、健康面でのリスクが発生するのも事実です。
たくさん飲酒することによる体への負担。

「たくさんお酒を飲むと体に悪い」となんとなくのイメージはあるかと思いますが、具体的にどういった健康面でのリスクを高めるのか、知っておいたほうがよいでしょう。
お酒は少量でも病気の発症リスクを上げる。
厚生労働省の「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」によると、たとえ少しの飲酒量であっても、高血圧・胃がん・食道がん・脳出血といった病気のリスクがあると指摘されています。週150gの純アルコール摂取量だと、前立腺がん・大腸がんなどが加わります。厚生労働省としては、「お酒は飲まないに越したことはない」という立場をとっています。
参考:厚生労働省「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」(2024年)
不調が出るのは、肝臓よりもまず胃腸から。
お酒による影響が出るのは肝臓というイメージを持つ人が多いと思いますが、肝臓は「沈黙の臓器」といわれ、異常があっても自覚症状が出にくいもの。黄疸などの明らかな症状が出るころには病気がかなり進行している恐れがあります。
一般的に、お酒を飲みすぎればまず胃や腸に異常が現れます。胃もたれや腹痛などの不調を無視して長期にわたり飲み続けていると、脂肪肝、そして肝硬変へと進む危険があり、その段階でようやく肝臓の異常に対する自覚症状が出るのです。
生活習慣病につながる、肥満のきっかけに。
お酒自体はそこまでカロリーは高くありませんが、それでもお酒を飲むことで太りやすくなる人は多いです。その理由としては、まず飲酒により食欲が増進するからです。また体がアルコールを分解している間は、脂肪の分解が抑えられるため、お酒とともに食べた脂肪分の代謝が遅くなります。つまり、問題はアルコールそのものよりも、一緒に食べる食事にあるといえます。
そうして肥満体型になると、肝臓にも中性脂肪が溜まりやすく、脂肪肝になりやすいです。脂肪肝は、心疾患をはじめとしたさまざまな生活習慣病の引き金となるリスクがありますから、注意が必要です。
「ついつい飲んじゃう」人が健康を守るためのコツ。

ここまでお酒のデメリットを挙げてきましたが、それでも「ついつい飲んじゃう」「飲み会の頻度がやっぱり多くて……」という人にむけて、いくつか健康を守るためのコツをお伝えします。
まずは、自分の適量を知ること。
前述の通りお酒への耐性は個人差が大きく、わずかでも飲めば不調をきたす人から、毎日それなりに飲んでも健康に過ごしている人もいます。
したがって、まず大切なのは自分の適量を知ることです。何を何杯くらい飲むと翌日までお酒が残るのか、どれほど影響が出るのか、常に意識しておくといいと思います。そうはいっても、ついつい飲んでしまう気持ちは私もよくわかります。しかし、できればほろ酔いの段階でお酒を止めるようにすると、比較的影響は少ないでしょう。
会食や飲み会が多い人は、ノンアルコールをはさむ。
どうしても飲む機会が多いなら、そのときどきでのアルコール摂取量を調整する必要があります。たとえば、お酒の合間にノンアルコール飲料をはさんだり、水や炭酸水をたくさん飲むようにしたりして、その場で飲むアルコール量を減らすようにするといいと思います。
ある程度お酒が進んでくると、味覚は鈍くなり、お酒の味があまりわからなくなるはずです。それでも飲み続けるのは、「なんだか口が寂しいから」という、惰性によるところが大きいと思います。そんなとき、お酒をノンアルコール飲料に変えても大した違いは感じづらいでしょう。
私も晩酌では、甘くないシークヮーサー果汁を炭酸に入れたものをお酒代わりに飲んで、飲みすぎを防止したりしていますよ。
【まとめ】お酒とうまく付き合うため、事前に休肝日を決めよう。
繰り返しになりますが、お酒との付き合いを考える上で大切なのは、「トータルのアルコール摂取量をいかに減らすか」です。その意味で、休肝日をつくればそれだけ体の負担を減らすことができます。なお、休肝日は思い付きで実施するより、週に1日でも、曜日を決めるなどして、スケジュールにあらかじめ組み込んでおくほうがしっかり守れるはずです。
お酒は「酔うため」ではなく、「おいしく味わうため」に飲むことをおすすめします。惰性で飲み続けず、ほろ酔いでなるべく止めておくのが、健康に末永くお酒を楽しむためのいちばんの秘訣かもしれません。
写真/PIXTA
【監修者】浅部 伸一
東京大学医学部卒業。国立がん研究センターで肝炎ウイルス研究に従事後、自治医科大学を経て、アメリカ・サンディエゴに留学。現在はアシュラスメディカル株式会社に在籍。自治医科大学附属さいたま医療センター消化器内科非常勤講師も務める。『酒好き医師が教える最高の飲み方』(日経BP社、2017年)などを監修。
※ この記事は、ミラシル編集部が取材をもとに、制作したものです。
※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。
※ 記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。