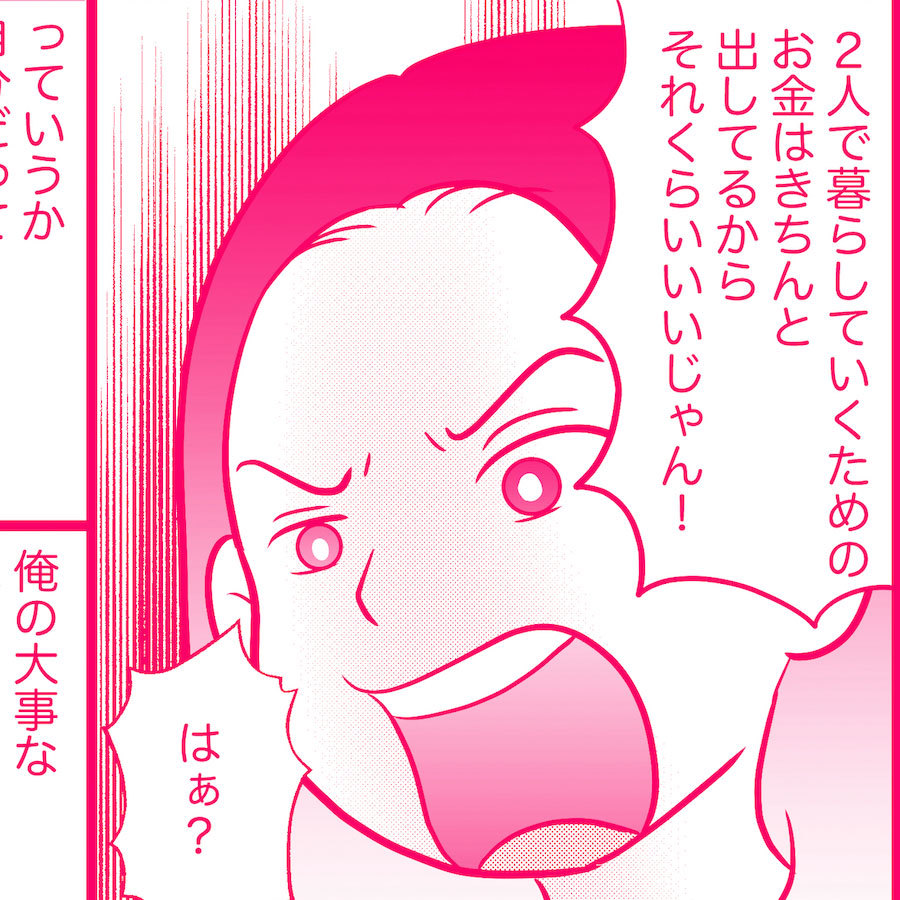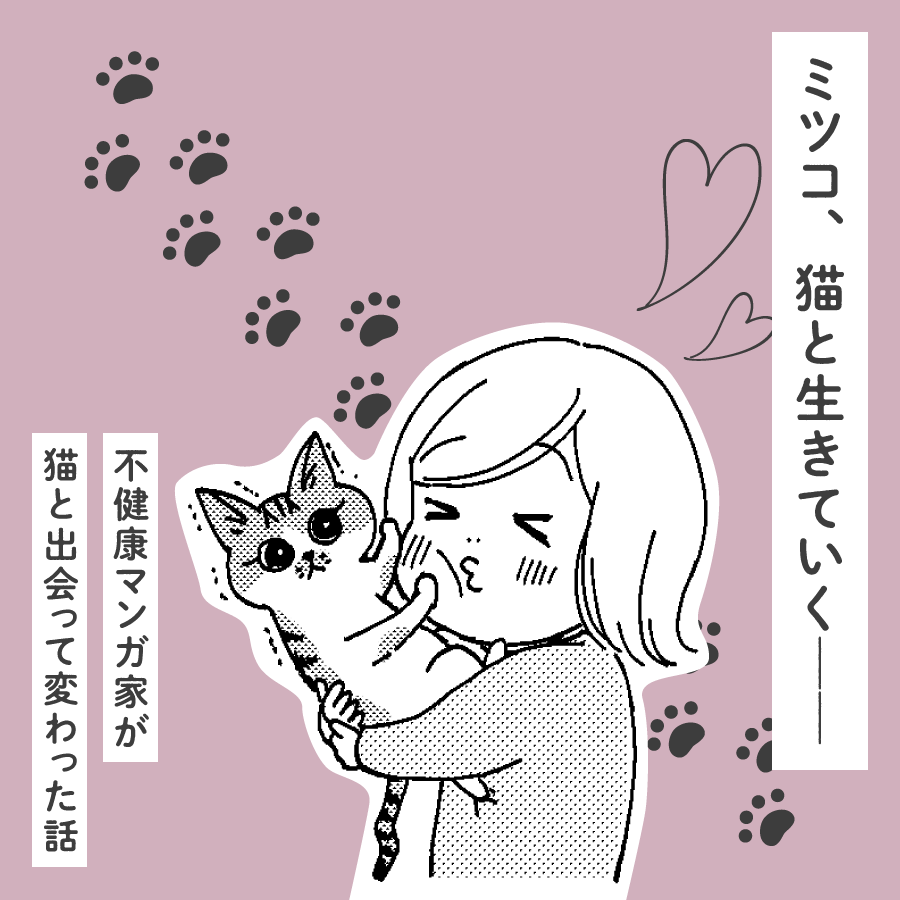(前編)犬山紙子 20代での母の介護とエッセイストデビュー、30代での育児。私が私らしくなるまで。
執筆活動やテレビ番組でのコメンテーターをはじめ、多くのメディアで活躍する犬山紙子さんには、これまで3つの大きな転機がありました。1つ目は新卒入社2年目で訪れた母の介護生活。2つ目は30代を目前に発刊したエッセイ集『負け美女 ルックスが仇になる』の出版。そして3つ目が2017年の出産。人生を揺るがす転機を乗り越えるたび自由を手にしてきた犬山さんに、ペルー料理店で束の間のひとときを過ごしているところへお邪魔して、これまでとこれからについて伺いました。
要介護の母に寄り添った20代。
──お母様の介護は20代で迎えていますね?
はい。大学生のときに難病がわかり、本格的に介護をするようになったのが社会人2年目のことでした。そのころは実家のある宮城で夢だった出版社での編集業に携わっていたので、突然の出来事にとても混乱しました。姉は東京で仕事をしていて弟は海外留学中と、当時の状況的に母を看られるのは私だけでしたし。家族の介護をする人、特に若い世代の人がキャリアに関する悩みを相談できる場所もなく、選択肢のないなかで介護生活に入ったというのが正直なところでした。
──犬山さんだけがご実家に残られたんですね。
最初の1年目はヘルパーさんと私だけ。でも心身ともに疲れて無理を感じたので姉と弟に相談すると、ほどなく姉が戻ってきてくれました。のちに弟も海外から戻り、3人で順番に看る形になったんです。
──ご自宅での介護は犬山さんが選ばれたと伺いました。
実際には姉と弟を含め3人で、予想される病状を踏まえて決めました。母はシャイ・ドレーガー症候群という難病だったんです。病状はパーキンソン病に似ているんですけれど、徐々に動作が緩慢になり、車椅子が必要となり、やがて寝たきりになるというもので。急変しないため入院の必要はなく、まずは自宅で普通に生活していました。のちに脳出血を起こし本格的な自宅での介護生活に入っていくんですが、そのときにも3人で「お母さんと一緒に家で暮らそう」と話しをして決めました。

──社会人となり、これからというタイミングです。「なぜ私だけ?」といった気持ちはありませんでしたか?
ものすごく焦っていた気がします。同世代の人たちがキラキラと将来につながるキャリアを積み、充実した日々を送っているように私の目には見えていました。一方で私の将来はどうなるんだろうと……。それに当時の私は父に生活費を出してもらっていたことに対して、なぜか「親のすねをかじって生きている」と自虐的に感じていたんです。よくよく考えれば、アルバイトをする余裕すらなく介護をがんばっていたのに。自分で働き、収入を得ていなかったことに後ろめたさを感じ、だから自信をもてないしフラストレーションが溜まる。その心の不安定さが危ういと思っていて、そのため母の介護をしながらでもかなう「自分のしたい仕事」とはなんだろう。そう問い続けて、「書き物をやりたい」という気持ちにたどり着けたんです。
ブログ本の出版で激変した生活。
──ご自身がニート時代と言われる6年間は、結果として助走期間となりました。
なんとか芽が出ないかなと6年間。ギリギリでしたね、時間的にも精神的にも。当時は「30歳になるまで」と勝手にリミットを決めていたんです。でも今思うと、29歳で『負け美女 ルックスが仇になる』が出せなくてもズルズルと続けていた気がします。介護と両立可能な融通の利く仕事で、かつ自分のやりたいこと。そう思うとほかに選択肢はありませんでしたし。それに夢をもっていないと心がもたない暮らしでしたから。当時は、自分のキャリアを考えることさえできないくらい、目の前の介護に追い詰められた日々でした。夢を目指すことは、生きる原動力の1つ。そういうものだった気がしますね。
──その『負け美女〜』は話題になりました。
はい。友人たちの恋愛模様をエッセイにしたためた本でした。生活は大きく変わりましたね。仕事面では、本を出した翌月にはテレビ出演もするようになったんです。その後もトントン拍子にレギュラーが決まったりして。執筆とテレビの仕事が並走しながら増えていった印象でした。でも何より、自分に仕事があるということが激しくうれしかったですね。
──生活面はどう変わりましたか?
東京にいる時間が増えました。それまでは月20日間は実家で、10日間が姉の借りていた東京のアパート。それが逆になった感じです。アパートは中目黒にあって、不摂生に暮らしていましたね(笑)。仕事が終わったら並木橋の「アマランスラウンジ」によく飲みに行って。そこはドラァグクイーンたちが働いている私にとって自由の象徴のようなお店なんですけど、「私、今仕事の帰りに飲んでる」という、その状況自体がすごくうれしかったんです。
──介護生活で過ごした10年を取り戻すように?
そうですね。結婚してからも子どもが生まれるまで生活は変わることなく、30歳から35歳まではそのような感じで。友達を家に呼んでずっとボードゲームをしたりとか、大好きなハロプロを応援したりとか。「あっ、青春ってこんな感じなのかな」と思う時間を過ごしていました。本当に自由を感じていました。

──そして恋愛がテーマだった『負け美女〜』とは変わり、30代に入ると社会的なテーマが増えた印象です。
社会が見えるようになってきたからだと思います。その頃にこの『負け美女』というタイトルにも反省するようになりました。内容は「友人たちのリアルを見ていると、美女だから人生イージーモードだなんて、そんな簡単な話じゃない」というものですが、人を勝ち負けでわけている、ルッキズム丸出しだったな、と。また、30代になって周囲の女性たちが「女性であるがゆえに経験する苦しさ」みたいなものをすごく語っていたんですね。「女性は結婚して子どもを産むことが幸せだ」という押しつけや、「女性の上司がぜんぜんいない」という会社のリアルな状況。男性にも「男性らしさ」を押しつけられ苦しんでる人がいて。そのあたりからジェンダー問題や、多様性への不寛容など、社会に潜むゆがみがクリアに見えてきた気がします。
母となり生まれた“備え”への意識。
──3つ目の転機が2017年の出産です。
このときは介護の経験が生きました。「自分だけでやろうとしたら潰れる」ことを嫌というほどわかっていたので、まずまわりの人に頼ることを考えました。夫とは前もって育児の役割を決め、民間の育児サービスも事前にかなり調べました。おかげで出産後は振り回されて大変という印象はなく、自分の時間もきちんと持てた感じです。あ、でも保活(子どもを保育所に入れるための諸活動)はほんとうに大変でした‥…。それに、家族が増えたことや、まだ幼い娘の命を守らなければならないことにプレッシャーは感じます。この状況が娘の成人まで続くと考え、経済面を支えるうえで、あと20年近くはがんばらないと。そう思うようになりました。

──産休や育休中は、勝ち取ってきた仕事への不安はありましたか?
めちゃくちゃありました。やっぱり出産、妊娠を機に、会社勤めをしている人ですらキャリアを築けなくなる現状があることを聞いていましたし。フリーランスの私の場合、書き物仕事はそれで切れるわけではないですが、テレビや講演など出演する仕事は休む必要があります。不在となった場は誰かが埋めることになるので、休んで復帰したとして仕事はあるのだろうか? そのような不安はありました。実際には復帰できた仕事もあり、これは本当にありがたい話で、仕事を依頼してくれる方のおかげでしかありません。
──現状、ご夫婦でフリーランス。備えやたくわえへの意識は変わりましたか?
今とても保険が気になる存在になってきていて、まさに検討しているタイミングなんです。フリーランスは保証のない職業。年金があるとはいえ、そこまで期待できないのが現状です。それに母が難病を抱えたのが47歳で、私が今年40歳になるので、あと7年。もちろん私が母のように病魔に襲われるとは限らないんですが、いつ何が起こるかはわからない。その怖さは娘が生まれてもっと強くなった気がしますし、「家族のためにたくわえておかないと」という気持ちも強まりました。
──学資保険についてはどうでしょうか?
最近まわりからよく話が出るようになって身近に感じています。今は娘用の口座をつくり、娘に関すること以外では使ってはいけないルールを設けています。そのたくわえを学資保険に変えるか、まさに現在検討中です。若いころは貯金をがんばっておけばいいと思っていたんです。でも出産以降、予想外の出費が多くて……。きちんと備える必要があるのかなと、生命保険も学資保険も同様に初心者段階で、いろいろと検討しているところなんです。

インタビュー後編では、目下、家庭内の大きな話題になっているお子さんの習いごとの話や、児童虐待の根絶を目指すため立ち上げたチームのこと。そして、ご自身の未来についてお話を伺いました。
テキスト:小山内隆 写真:三浦咲恵 取材協力:荒井商店
犬山 紙子
いぬやま・かみこ●1981年生まれ、大阪府出身。イラストエッセイスト、コラムニスト、コメンテーター。大学卒業後にファッション誌の編集者に。2011年、『負け美女ルックスが仇になる』(マガジンハウス)でデビュー。以降、TV、ラジオ、雑誌、Webなどで活動中。2014年に結婚し、2017年に第一子となる長女を出産。2018年、児童虐待問題に声を上げるタレントチーム「#こどものいのちはこどものもの」を発足。社会的養護を必要とする子どもたちにクラウドファンディングで支援を届けるプログラム「こどもギフト」のメンバーとしても活動中。