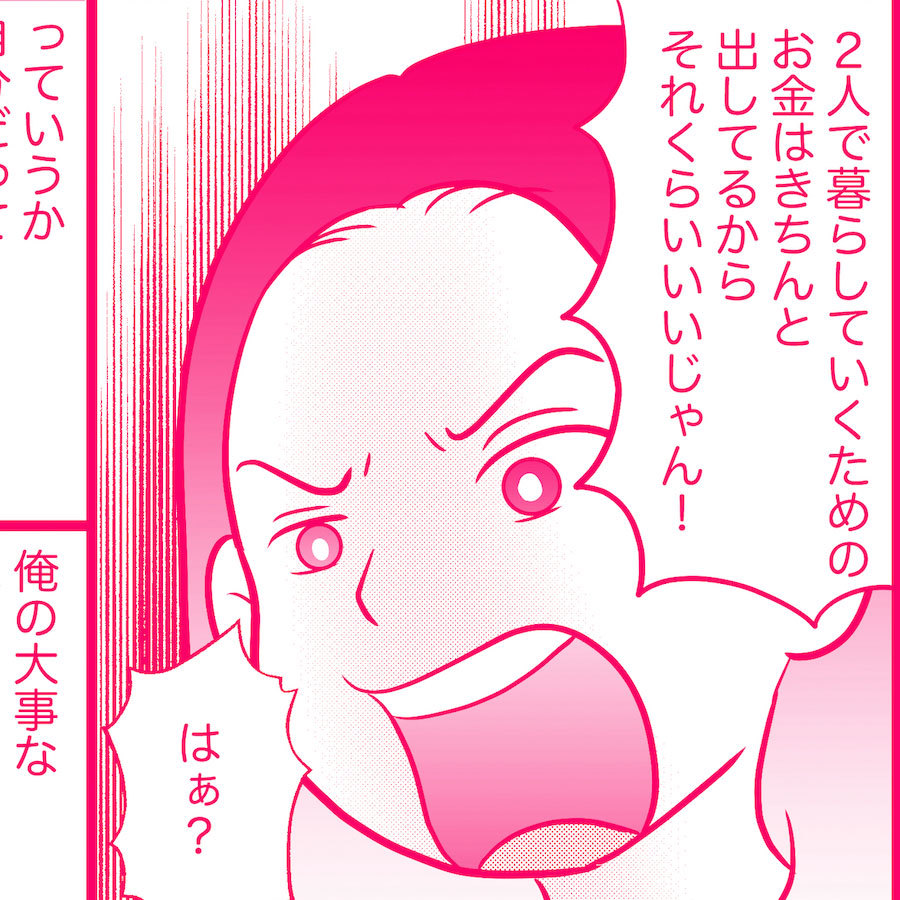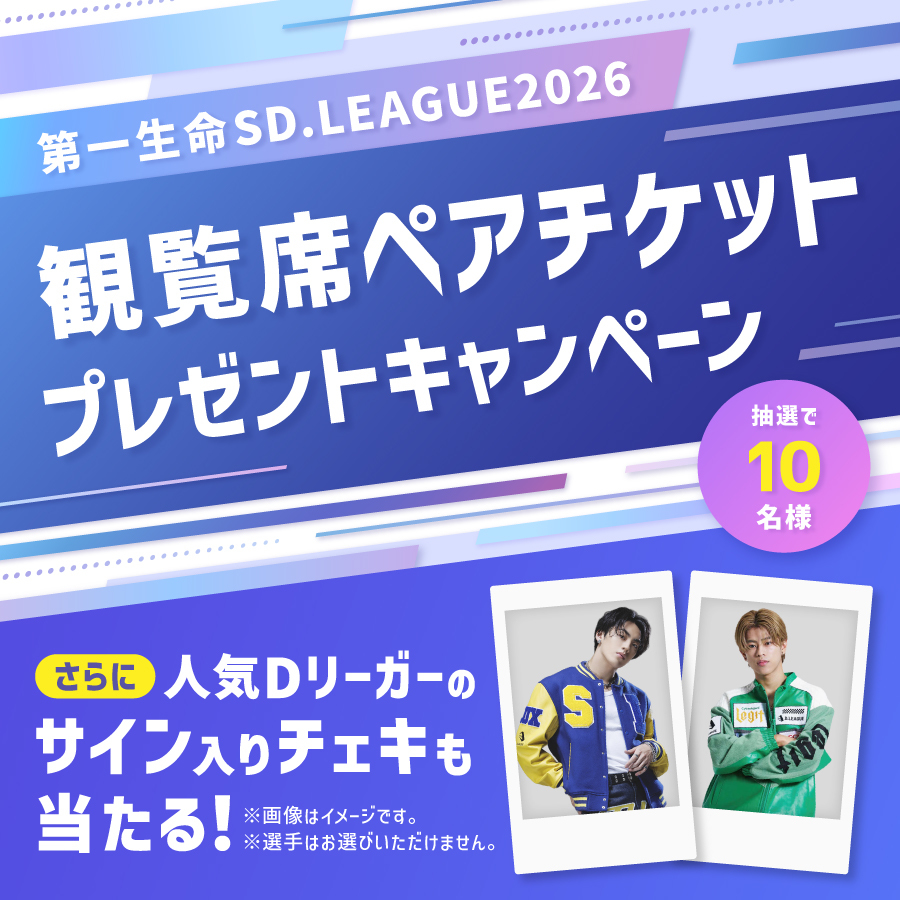酒粕甘酒の効果とは?米麹甘酒との違いは?甘酒ソムリエが解説。
「飲む点滴」とも呼ばれ、健康や美容効果が期待できるスーパードリンクとして人気のある甘酒。しかし「酒粕甘酒と米麹甘酒、どっちを飲めばいいの?」「実際にどのような効果があるの?」など、甘酒について疑問を持つ方も多いのでは?
この記事では、甘酒の中でも、酒粕の風味が特徴的で家でも簡単につくれる酒粕甘酒にスポットを当て、米麹甘酒との効果の違いや、酒粕甘酒の飲み方、家で手軽に実践できるつくり方などをご紹介。甘酒ソムリエ・甘酒探求家の藤井寛さんが解説します。
目次
甘酒の種類は2つ。

甘酒には、酒粕でつくる「酒粕甘酒」と、米麹でつくる「米麹甘酒」の2種類があります。下の表のように、原料や味、食感などに大きな違いがあります。
酒粕甘酒と米麹甘酒の比較
| 種類 | 酒粕甘酒 | 米麹甘酒 |
| 原料 | 酒粕・砂糖・水 | 米・米麹・水 |
| 主な栄養素 | たんぱく質・ビタミンB群、食物繊維など | ブドウ糖・オリゴ糖・アミノ酸・ビタミンB群・食物繊維など |
| アルコール | 微量に含まれる | なし |
| 味・香り | 砂糖の甘さ・日本酒の香り | 米と米麹の自然でほのかな甘さと香り |
| 食感 | とろりとした食感 | 米の粒が残っていることがある |
| 主な効果 | 肥満・血圧上昇・健忘症の抑制など | 整腸作用・栄養補給など |
酒粕甘酒
酒粕甘酒は、日本酒をつくる際に出る酒粕を使ってつくる甘酒です。酒粕は、麹菌や酵母などの働きにより、栄養面や機能面で魅力ある食材となっています。また、酒粕にはもともと甘みがないため、つくるときはお湯に溶かし、砂糖などで甘みを加えます。家庭でも手軽につくれるのが特徴です。
酒粕甘酒は、酒粕ならではの風味と日本酒の香りが楽しめるのが魅力ですが、それを苦手に感じる人もいるかもしれません。ただし、酒粕の種類によって香りや風味が異なるため、自分の好みに合うものを選ぶことも可能です。また、加熱することでアルコールはほとんど飛ぶため、お酒が苦手な人でも飲みやすくなります。
米麹甘酒
米麹甘酒は、米・米麹・水を一晩かけて発酵させてつくる甘酒です。米麹の酵素が米のデンプンを分解・糖化するため、砂糖を入れなくても自然のやさしい甘みを楽しめます。
できたては米の粒が残りますが、ミキサーやブレンダーにかけるとなめらかな口当たりに。ブドウ糖が豊富で、素早くエネルギー補給ができるのも大きな特徴です。
酒粕甘酒ならではの効果とは?米麹甘酒との違いは?

甘酒は健康や美容に効果があると聞いたことがある方も多いかもしれません。実際に、酒粕甘酒にはどのような効果があるのでしょう。酒粕甘酒ならではの効果について、見ていきましょう。
ビタミンB群で代謝促進・お肌の健康を保つ。
酒粕甘酒には、たんぱく質やビタミンB群(ビタミンB1・ビタミンB2・ナイアシン・パントテン酸など)が、米麹甘酒よりも豊富に含まれています。
ビタミンB群には、糖質やたんぱく質、脂質などの代謝をサポートして、だるさや疲労を軽減するほか、皮膚や粘膜のターンオーバー(新陳代謝)を促進し、お肌の健康を保つ効果があります。
参考:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 第2章(データ)」
食物繊維で腸内環境を整える!コレステロールの低下も。
酒粕甘酒には、食物繊維も豊富に含まれており、その量は米麹甘酒の3.7倍ほど。食物繊維には整腸作用があり、便秘の改善やコレステロール低下、免疫力向上の効果があります。
参考:文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年 第2章(データ)」
また、酒粕甘酒には「レジスタントプロテイン」という、食物繊維と似た働きをする消化されにくいたんぱく質が豊富に含まれています。レジスタントプロテインには腸内環境を整え、コレステロールを低下させたり、肥満を抑制したりする作用があることが知られています。
酒粕甘酒の気になる疑問や注意点。

酒粕甘酒をより効果的に生活に取り入れるためには、1日どれくらいの量を飲めばいいのでしょうか。また、飲むべきタイミングについてもみていきましょう。
1日どのくらい飲んでいいの?
コップ1杯200mlの酒粕甘酒のカロリーは、含まれる砂糖の量に大きく左右されるものの大体200kcal。1日の摂取量の目安はコップ1杯程度になります(※)。
酒粕甘酒に豊富に含まれるビタミンB群は、摂取しても体内にとどまる時間が短い性質があります。そのため、一度にたくさん飲むのではなく、毎日の食生活に取り込み、適量を継続して飲むことをおすすめします。
※ 成人の菓子・嗜好飲料の摂取目安は1日200kcal程度。
飲むのにベストなタイミングは?
酒粕甘酒に限らず、甘酒全般について言えば、飲むタイミングは朝がおすすめです。朝に甘酒を飲むと、脳にエネルギーが供給され、血糖値が上がることで、体内時計がリセットされ体が目覚めます。忙しくて時間がないときや食欲がないときでも、甘酒を1杯飲むだけで栄養を速やかに摂取できます。
ただし、酒粕甘酒はアルコールが含まれているため、アルコールに弱い人や運転をする人は注意が必要です。
酒粕甘酒のつくり方。コツや酒粕選びのポイントは?

一見、手間がかかりそうな酒粕甘酒づくりですが、お湯に酒粕と甘味料を入れて溶かすだけで、お家でも簡単につくることができます。ぜひ試してみてください。
酒粕甘酒のつくり方。
【材料(酒粕甘酒500ml)】
・酒粕:100g
・水:400ml
・砂糖:50g~100g(量はお好みで調整)
・塩:ひとつまみ
・生姜:お好みの量
1. 鍋にお湯をわかし、沸騰したら火を止める。
2. お湯に酒粕を入れ、しっかり溶かす。
3. 砂糖と、お好みで塩や生姜を入れて味をととのえる。
4. 火をつけて、弱火で1分~2分沸騰させ、アルコールを飛ばして完成。
酒粕甘酒をつくるときのコツ。
コツは酒粕を溶かし入れるときに、いったん火を止めること。味噌汁をつくるときも、風味を損なわないように、火を止めてから味噌を入れますよね。それと同じ原理です。
酒粕を入れたあとで再度加熱しますが、グツグツ煮立たせすぎると酒粕の風味が飛んでしまうのでご注意を。
また、「砂糖をあまり使いたくない」という方は、好みに応じてハチミツ・きび糖・黒糖・オリゴ糖などに置き換えていただいてもOKです。米麹甘酒と混ぜて飲んでも、自然な甘さを楽しめるのでおすすめです。塩をごく少量加えると、甘みが引き立つのでぜひお試しください。
酒粕選びのポイントは?
酒粕には、固い板状の「板粕」のほか、ボロボロしており柔らかい「バラ粕」、熟成させたペースト状の「練り粕」の主に3種類があります。
成分に大きな違いはありませんが、家庭で酒粕甘酒をつくる際は、お湯に溶かしやすいバラ粕か練り粕がおすすめです。板粕は水に溶かすのが少々大変なので、そのぶん、手間がかかってしまうことも。
本醸造酒や普通酒、吟醸酒などいろいろな日本酒の酒粕がありますが、それぞれ香りが大きく違います。スーパーで1年中手に入る大手酒造メーカーの酒粕ももちろんおいしいですし、地方の酒蔵にあるご当地酒粕や、限られた時期にしか出回らない有名ブランドの高級酒粕などを試してみるのもおもしろいですよ。ぜひ好みの酒粕を探してみてください。
手づくりした甘酒の日持ちはどのくらい?
冷蔵庫で2日~3日が目安です。冷凍庫で凍らせると長持ちしますが、庫内の匂いがうつって香りが損なわれる可能性があるので、およそ3か月以内を目安に飲みきってください。
【まとめ】酒粕甘酒を毎日の習慣に。
栄養豊富な酒粕甘酒は、忙しい日々でも手軽に取り入れられる優れた飲みもの。自宅で簡単につくれるので、時間がないときでも気軽に楽しめます。さらに、自分好みにアレンジできるのも魅力の1つ。日々の健康と美容のために、ぜひ“甘酒生活”をはじめてみてはいかがでしょうか。
写真/PIXTA
【監修者】藤井 寛
1985年生まれ。東京農業大学大学院農学研究科食品栄養学専攻博士前期課程修了。大学院卒業後に食品関連の研究職に携わり、その後甘酒の探求に専念。甘酒探求家として全国の市販甘酒をレビューするほか、自作の甘酒研究に努める。著書に『元気をつくる!麹の甘酒図鑑』(主婦の友社)、『甘酒のほん 知る、味わう、たずねる』(山川出版社)など。
※ この記事は、ミラシル編集部が取材をもとに、制作したものです。
※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。
※ 記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。