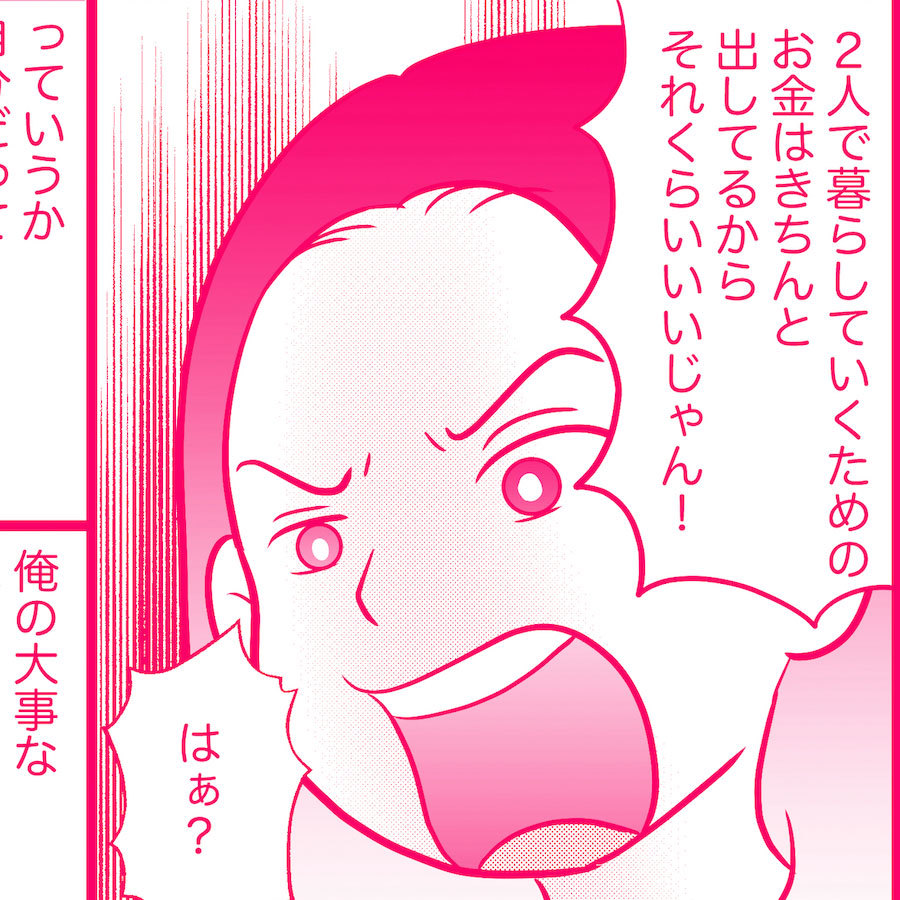ハイハイはいつから?成長のステップややる気を引き出すコツを解説
赤ちゃんのトレードマークのようなイメージがある「ハイハイ」。わが子がハイハイをいつからはじめるのか気になる親御さんは多いはず。
でも、なかなかハイハイをしなかったり、ほかの子よりも早くつたい歩きをはじめてハイハイをする期間が短かったりすると、「月齢にあった発達をしている?」「もっとたくさんハイハイをさせたほうがいい?」と心配になることも。
ママやパパが気になる赤ちゃんのハイハイについて、子どもの心身の発達を研究している小児科医の榊原洋一先生が解説します。
目次
「ハイハイはいつから?」と焦る必要なし。

ハイハイをいつからはじめるかについて、母子健康手帳にはだいたい月齢7か月~10か月が多いと書かれています。この時期を過ぎてもハイハイをはじめない子どもを持つ親が「うちの子は発達が遅れている?」と心配になるのは当然のことかと思います。
参考:こども家庭庁「母子健康手帳省令様式(令和6年4月1日施行)」(参照:2024年10月15日)
しかし、実はハイハイは順調な運動発達の過程で必ずしなくてはいけない動きではありません。ハイハイをまったくしない赤ちゃんも、やがて立ち上がり、ひとり歩きをはじめることがわかっています。
赤ちゃんの運動発達はステップが大事。

赤ちゃんの運動発達でまず心得ておきたいことはざっくり2点あります。
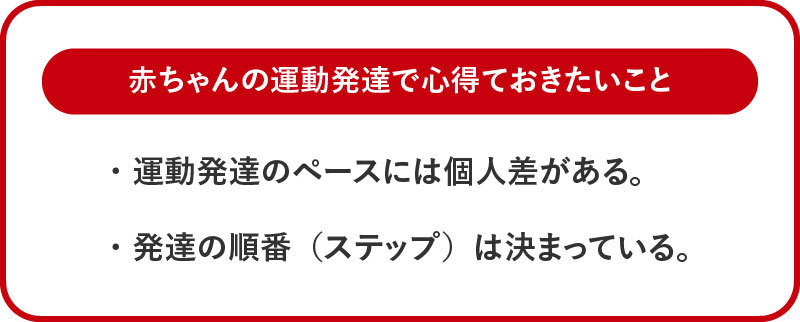
以下、詳しく説明します。
運動発達のペースには個人差がある。
首すわり・寝返り・おすわり・つかまり立ち・ひとり歩きは、赤ちゃんが順調に発達していることを示す、とても重要な指標です。
たとえば、寝返りなら全体の3分の2くらいの子が、月齢4か月~6か月ごろのどこかのタイミングでできるようになります。順調な発達をしている赤ちゃんでも、それぞれの運動ができるようになる時期には個人差があるのです。
発達の順番(ステップ)は決まっている。
赤ちゃんの随意運動(自分の意思で行う運動)の発達は、体の上(頭)のほうから下へと進みます。頭→首→胸・背中→腰→脚→足と、自分の意思で動かせるようになっていくため、首すわり・寝返り・おすわり・つかまり立ち・ひとり歩きは、必ずこの順番でできるようになります。
寝返りは4か月~6か月ごろ。
生まれてからずっとあおむけの姿勢で寝ていた赤ちゃんは、首がすわり、周囲への関心が高まって、頭の上のほうにある何かを見ようと背を反らせたときなどにクルッと体ごとまわって寝返りができるようになります。だんだんにコツをつかんで、あおむけからうつぶせ、うつぶせからあおむけと、自在に寝返りができるようになります。
腰すわりは5か月~8か月ごろ。
大人がすわらせても、腰や背中を支えてあげないとすぐに倒れてしまっていた赤ちゃんも、運動発達が背中から腰へと進み、腰がすわってくるにつれ、前に手をついて少しの間、おすわりの姿勢を保てるようになります。
おすわりは7か月~9か月ごろ。
しっかり腰がすわると、おすわりの姿勢が安定して、両手で体を支える必要がなくなります。自由になった両方の手指で、いろいろな動作ができるようになります。また、うつぶせの姿勢から自分でおすわりするようになります。
ハイハイは運動発達のバイパスのようなもの。

ハイハイは、運動発達の過程で誰もが必ず通る道ではなく、経由する子もいればスキップする子もいる、バイパスのようなもの。
また、赤ちゃんによっていろいろなやり方があり、「これがハイハイの完成形」というものは決まっていません。おなかを床につけた「ずりばい」、手のひらと膝を床につけた「よつばい」、手のひらと足の裏を床につけておなかと腰を高く持ち上げる「高ばい」、そのほかにも子どもによっていろいろなハイハイのスタイルがあります。
また、冒頭でも述べたとおり、ハイハイは赤ちゃんの運動発達において、必ずしも重要な指標ではありません。ハイハイのスタイルはバリエーションがとても多く、まったくしない子もいるからです。
小児科医が発達の進み具合を確認するときに参照する指標にも、ハイハイの記載がないこともありますので、「月齢○か月なのに、まだハイハイしない」と心配する必要はないのです。
首すわり・寝返り・おすわりが順調にできているなら、ハイハイをしない子もいずれは順調に歩き出すケースがほとんどです。
また、ハイハイをしない子の中には「シャフリングベビー」と呼ばれる、おすわりの姿勢のままでおしりを引きずって移動する子もいます。歩きはじめが遅くなる傾向にはありますが、首すわり・寝返り・おすわりが順調に進んできたのであれば、遅くとも2歳ごろまでには歩きはじめ、その後の運動発達には問題のないことがわかっています。
ハイハイは赤ちゃんの移動手段の1つ。
赤ちゃんは「初めて見たものをより長く見つめる」ということがわかっています。「何だろう?」と好奇心を抱いて見つめ、手を伸ばし、もっと近寄ってみたい、触ってみたいという思いが、体を動かすモチベーションになります。
まだ歩けない赤ちゃんは、自分の体をどうにか動かして、行きたいほうに近づいていこうとします。寝返りの連続でゴロゴロと目的の場所まで移動する子もいれば、いろいろなスタイルのハイハイをする子もいます。おすわりしたままおしりで移動する子、おすわりからいきなりつかまり立ちをしてつたい歩きをはじめる子もいます。
ハイハイは、ひとり歩きをする前の赤ちゃんの移動手段の1つにすぎないのです。
ハイハイを促す練習は必要なし。

ハイハイをたくさんすることが、「立っち」や「ひとり歩き」をはじめる時期に影響したり、運動能力の向上につながったりすることはないと言われています。
信じられないかもしれませんが、南米には、赤ちゃんを1歳半ごろまで、親が働いている間は布でぐるぐる巻きにして動けなくしておく「スウォドリング」という育児法で子育てをしている民族がいます。赤ちゃんは、ハイハイどころかおすわりもしないで過ごすのですが、1歳半を過ぎたころに布を外すと、スタスタと歩きはじめます。
とても極端な例ですが、このことからも赤ちゃんはハイハイで鍛えたから歩けるようになるのではなく、時期が来れば歩くようになることが実証されているのです。
ですから、遊びのなかで赤ちゃんに楽しくハイハイを促してみるのもよいですが、無理に練習をさせる必要はありません。ハイハイ以外の移動方法でもまったく問題はないのです。
安全に動ける環境をつくり、やる気を引き出そう。
上記のとおり、ハイハイ自体が運動能力の発達につながることはないとされていますが、興味をひかれたものをめがけて自分から動いていくことは、認知の発達には意味があります。おもちゃに手を伸ばし、つかんだり触ったりすることで手先の器用さも育まれます。
赤ちゃんの動きたい、触りたい、ママやパパのほうに近づきたい、というモチベーションが高まるようなかかわり方をして、安全にのびのび動ける環境をつくってあげましょう。赤ちゃんが過ごす室内環境のほか、動きやすい服を着せてあげることも大事です。
大人のイメージどおりのハイハイでなくても、赤ちゃんの「動きたい」という気持ちのままに寝返りしたり、ハイハイしたり、おすわりのままで進んだりするのを「すごいね」「ママ(パパ)のところまで来られたね」と喜んであげましょう。大人も赤ちゃんの動作をまねっこして追いかけっこして遊ぶなど、楽しくかかわってあげればよいのです。
つかまり立ちをするようになったら、うまくつかまれる家具などがあるとよいですし、さらに高いところにまで手が届くようになるので、それに対応した安全対策が必要になります。
児童館・保育園などではまねっこを楽しむことも。
おうちが狭くて……という場合は児童館などに連れていくのもいいでしょう。広々とした安全なスペースで赤ちゃんは体を動かすことができます。
また、赤ちゃんは7か月~8か月ごろからまねっこを楽しむようになります。「保育園に入園したら、まわりの赤ちゃんがハイハイするのに刺激されたのか、突然うちの子もしはじめた」という経験をされたママ・パパもいます。
もちろん、個人差があり、ママやパパのまねっこをするのが大好きという子もいれば、動かずにじっとまわりの様子を見ているのが好き、というタイプの赤ちゃんもいます。1人ひとりに違う個性があります。「月齢○か月の赤ちゃんは□□するもの」という考えにとらわれず、その子ならではのペースで発達していく様子を見守っていきましょう。
【まとめ】心配なときは、小児科医に相談を。
ハイハイは、赤ちゃんの運動発達の過程で必ずできなくてはいけない運動ではありません。
ただし、ハイハイに限らず、寝返りやおすわりなどの運動がうまくできない背景に、筋肉や神経などの病気が隠れていることがあります。
こうした障害や病気では、発達全般の遅れや姿勢の不安定さなどが見られ、乳児健診で見つかる場合もあります。
親として、ちょっと何かが違うなと感じたり、育てにくさを感じたりして心配なときは、かかりつけの小児科医に相談してみてください。
写真/PIXTA
【監修者】榊原 洋一
医学博士。小児科医。お茶の水女子大学子ども発達教育研究センター教授を経て、同名誉教授。チャイルドリサーチネット所長。専門は小児科学、発達神経学、国際医療協力、育児学で発達障害研究の第一人者。著書は『ヒトの発達とは何か』(筑摩書房)など多数。
※ この記事は、ミラシル編集部が取材をもとに、制作したものです。
※ 掲載している情報は、記事公開時点での商品・法令・税制等に基づいて作成したものであり、将来、商品内容や法令、税制等が変更される可能性があります。
※ 記事内容の利用・実施に関しては、ご自身の責任のもとご判断ください。